
\コンテンツはこちら/
人気カテゴリ PICKUP!
- 事務雑務の時短
- プライベート・節約
- 資格・副業
- 就職・転職
- パパママ向け子育てトピック
運営中SNS

こんばんは!保育士のあつみです。
この記事では「0歳児クラス」の「1月」の月案の書き方・作り方や文例をたくさん紹介します。
保育所保育指針の5領域にも対応した文例もありますよ!
ぜひ、参考にしてみてくださいね。
読みたい【年齢・クラス】と【該当の月】を選んでタップorクリックくださいね。
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0歳児×4月 | 1歳児×4月 | 2歳児×4月 | 3歳児×4月 | 4歳児×4月 | 5歳児×4月 |
| 5月 | 0歳児×5月 | 1歳児×5月 | 2歳児×5月 | 3歳児×5月 | 4歳児×5月 | 5歳児×5月 |
| 6月 | 0歳児×6月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
| 7月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
| 8月 | 0歳児×8月 | 執筆中 | 2歳児×8月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
| 9月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
| 10月 | 0歳児×10月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
| 11月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
| 12月 | 0歳児×12月 | 1歳児×12月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
| 1月 | 0歳児×1月 | 1歳児×1月 | 2歳児×1月 | 3歳児×1月 | 執筆中 | 執筆中 |
| 2月 | 0歳児×2月 | 1歳児×2月 | 2歳児×2月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
| 3月 | 0歳児×3月 | 1歳児×3月 | 2歳児×3月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
クラスの年齢のタブを選んでね!
室内遊びの文例
外遊びの文例
\絵本をもっと探す/
\絵本専門店はこちら/
\登録者一万人突破~!/

0歳児クラスの1月の保育室の環境は、子どもたちの安全と快適さを最優先に考えるとともに、季節感や発達段階に合わせた遊びや活動ができるように工夫することが大切です。
新しい
1月を振り返ると、この月は多くの行事や季節を感じる活動を通じて、子どもたちの成長や変化を実感することができました。新年のお祝いとして、お餅つきの見学ました。初めての経験に、子どもたちは興味津々で触れ、新しい食材や食文化に親しむことができました。月齢の高い子は、杵でお餅をついたり、という体験も出来ました。
また、冬の季節を感じる遊びとして、室内での雪遊びや冬の絵本の読み聞かせを取り入れました。
絵本で見た内容を実際に遊んだり、散歩で探索したりして、子どもたちは季節の変化や自然の中での遊びの楽しさを学ぶ機会がふえるようにしていきました。
しかし、反省点としては、特に低月齢の子どもたちにとって、初めての経験が多いこの時期に、もう少し個別のケアやサポートが必要だったのではないかと感じました。特に、新しい食材や遊びに対する反応や適応の仕方は、一人一人異なるため、もう少し細やかな対応が求められると思います。
来月に向けては、2月は節分などの行事が控えています。子どもたちがこれらの行事を楽しみながら、新しい経験を積むことができるよう、計画的な保育を心掛けたいと思います。
また、今月の反省を踏まえて、個々の子どものニーズに応じたケアを提供することを重視し、より質の高い保育を目指していきたいと考えています。
休み明けには、情緒が落ち着いて登園する子どもが多く、発達に応じて個々の気持ちを受け止めることで、情緒の安定を図ることができました。冬の寒さから風邪をひく子がいたことや、感染症(胃腸炎)が発生した際には、保育室を消毒して迅速に対応しました。2月に向けては、職員間の連携をさらに強化し、環境衛生に配慮しながら、健康観察や家庭との連絡をこまめに行い、感染症の早期発見や適切な対応を心がけます。
今月は、室内での活動が中心でしたが、暖かい日には戸外での遊びも取り入れました。歩けるようになった子どもたちの行動範囲が広がり、探索活動を楽しむ姿が見られました。安全面に注意しながら、子どもたちの成長をサポートする環境づくりを続けます。
また、下痢をする子が多く見られたため、家庭との連絡を密にとり、子どもたちの健康状態を常に確認しました。今後も家庭との連携を深め、子どもたちの健康や発達を第一に考えた保育を展開していきます。
来月に向けて、季節の変わり目や行事に合わせたプログラムを計画し、子どもたちの成長をより一層サポートしていきたいと思います。


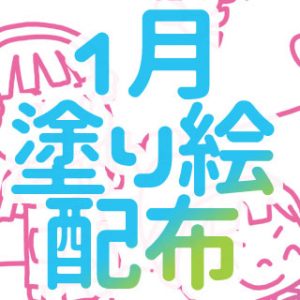
読みたい【年齢・クラス】と【該当の月】を選んでタップorクリックくださいね。
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0歳児×4月 | 1歳児×4月 | 2歳児×4月 | 3歳児×4月 | 4歳児×4月 | 5歳児×4月 |
| 5月 | 0歳児×5月 | 1歳児×5月 | 2歳児×5月 | 3歳児×5月 | 4歳児×5月 | 5歳児×5月 |
| 6月 | 0歳児×6月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
| 7月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
| 8月 | 0歳児×8月 | 執筆中 | 2歳児×8月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
| 9月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
| 10月 | 0歳児×10月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
| 11月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
| 12月 | 0歳児×12月 | 1歳児×12月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
| 1月 | 0歳児×1月 | 1歳児×1月 | 2歳児×1月 | 3歳児×1月 | 執筆中 | 執筆中 |
| 2月 | 0歳児×2月 | 1歳児×2月 | 2歳児×2月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
| 3月 | 0歳児×3月 | 1歳児×3月 | 2歳児×3月 | 執筆中 | 執筆中 | 執筆中 |
クラスの年齢のタブを選んでね!
この記事では、0歳児クラスの1月の月案の書き方のヒントや文例を提供しました。
季節の変わり目や子どもたちの成長の様子を踏まえながら、こちらの文例を活用し、自分のクラスの子どもたちの特性や状況に合わせてアレンジしてくださいね!
効率的な月案作成により、貴重な時間を節約し、その分、子どもたちとの関わりをより深く持つことができます。
子どもたちとの瞬間瞬間の関わりは、保育者にとっても子どもたちにとってもかけがえのない時間です。
この記事が、そんな大切な時間を増やす一助となれば幸いです!
 あつみ
あつみあつみ先生が超絶ブラック大規模園→小規模園へ転職した話…気になる方はこの記事で読んでみてね!

このたび、インスタアカウントを作りました♪
子どもの工作や手作り知育玩具の情報を配信してますので、チェックしてみてくださいね!
\ 今すぐ押してフォロー! /
\おしらせ!/


この記事が気に入ったら
フォローしてね!
提供中サービス
コメント